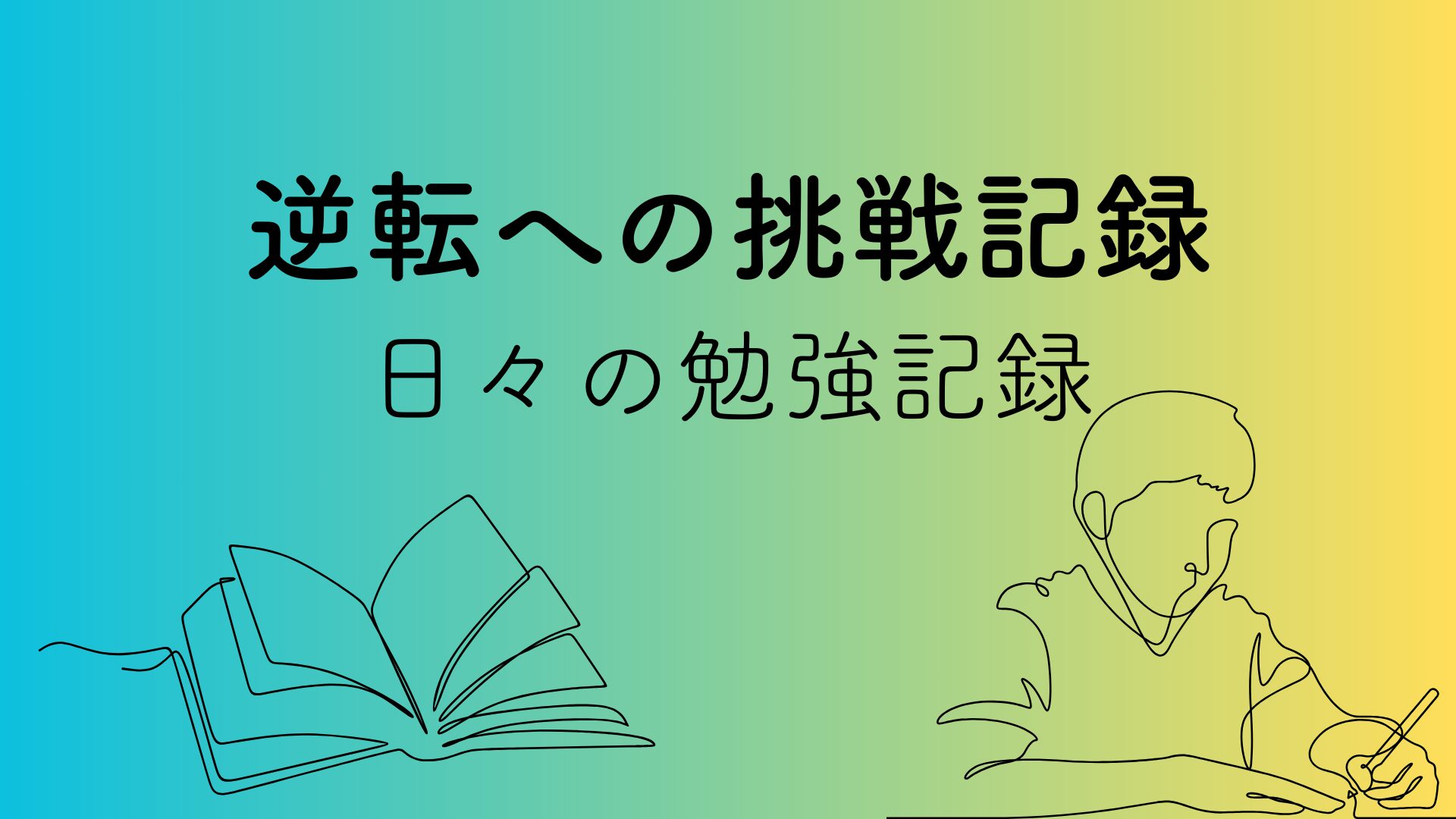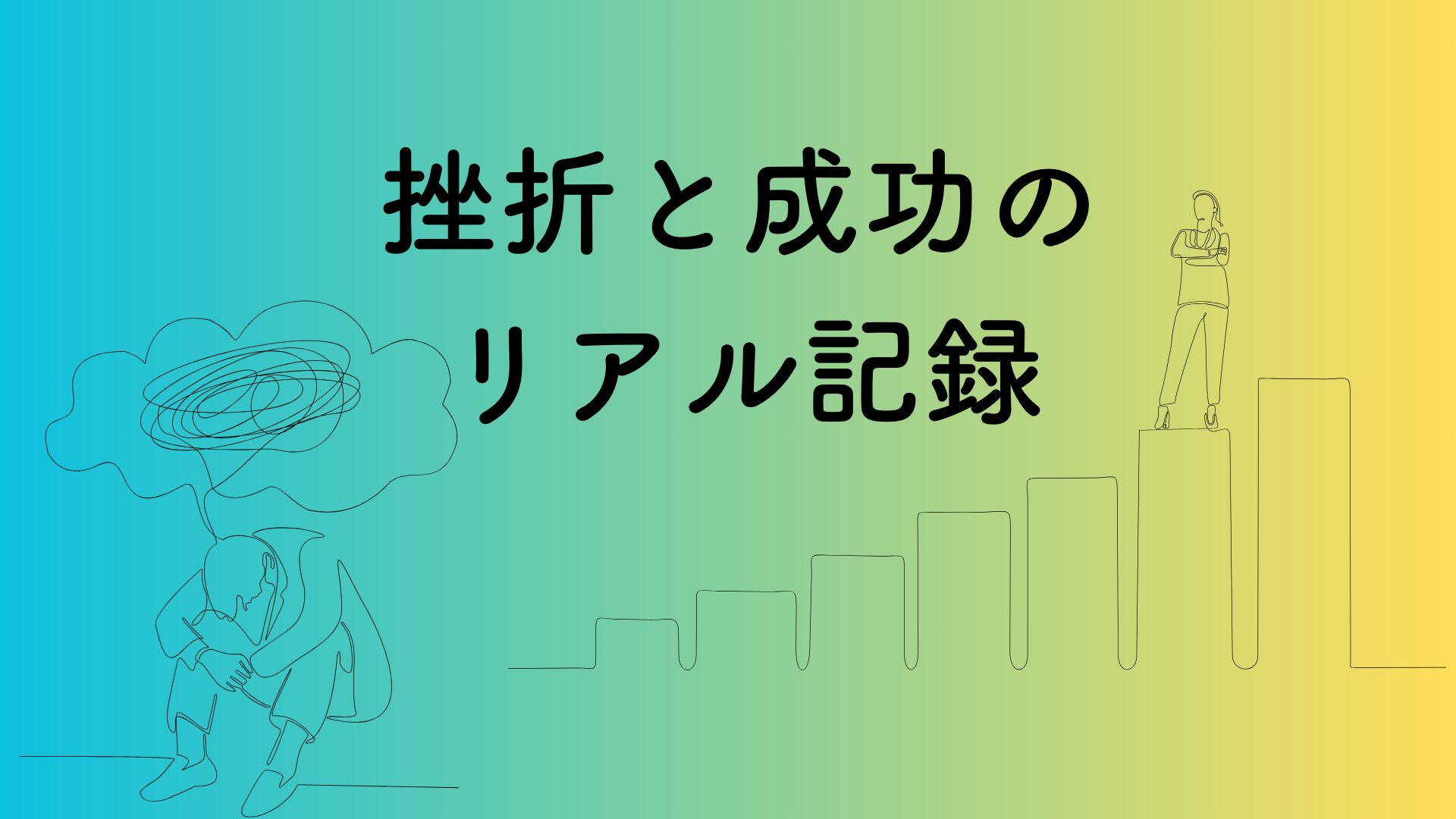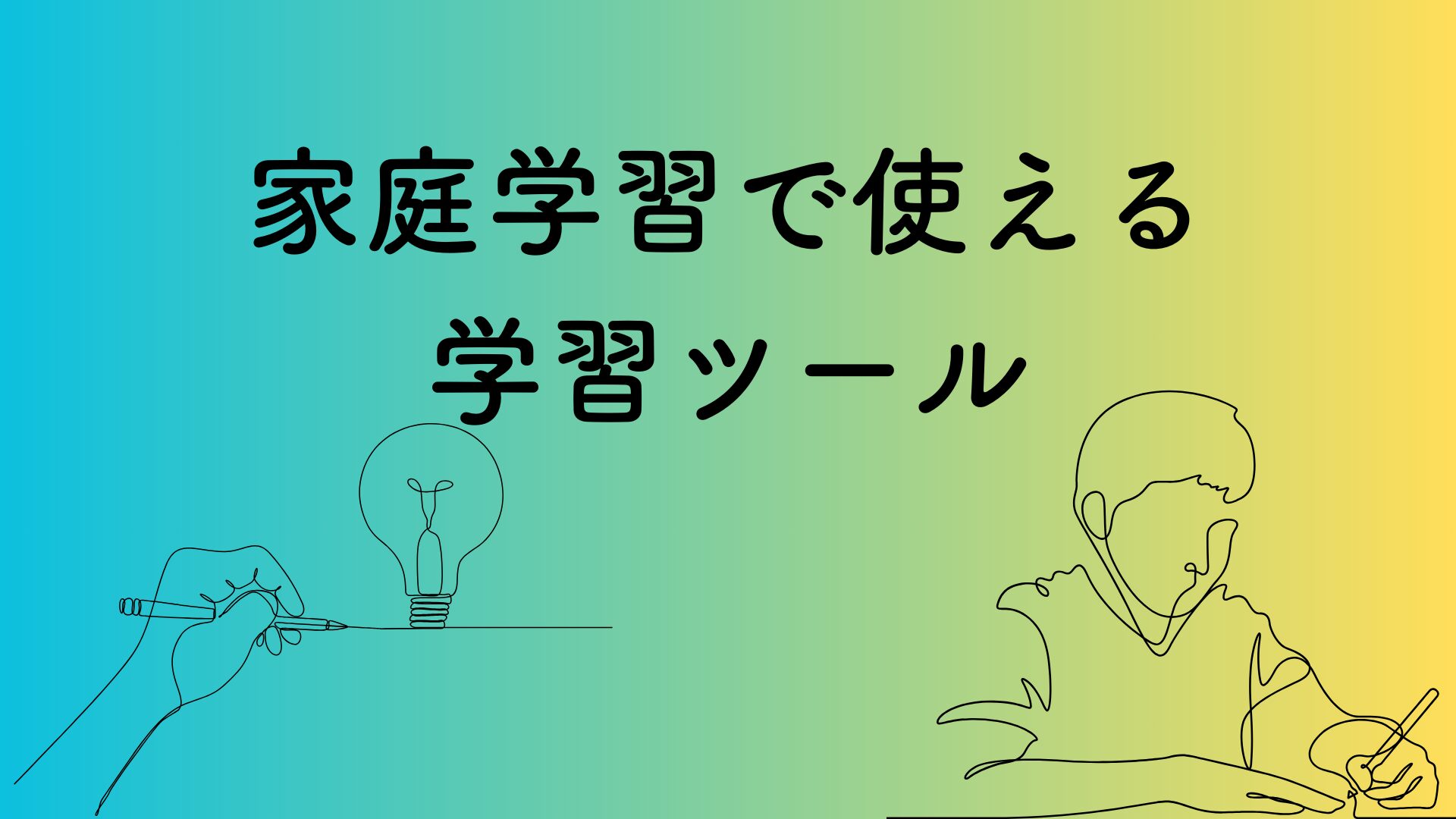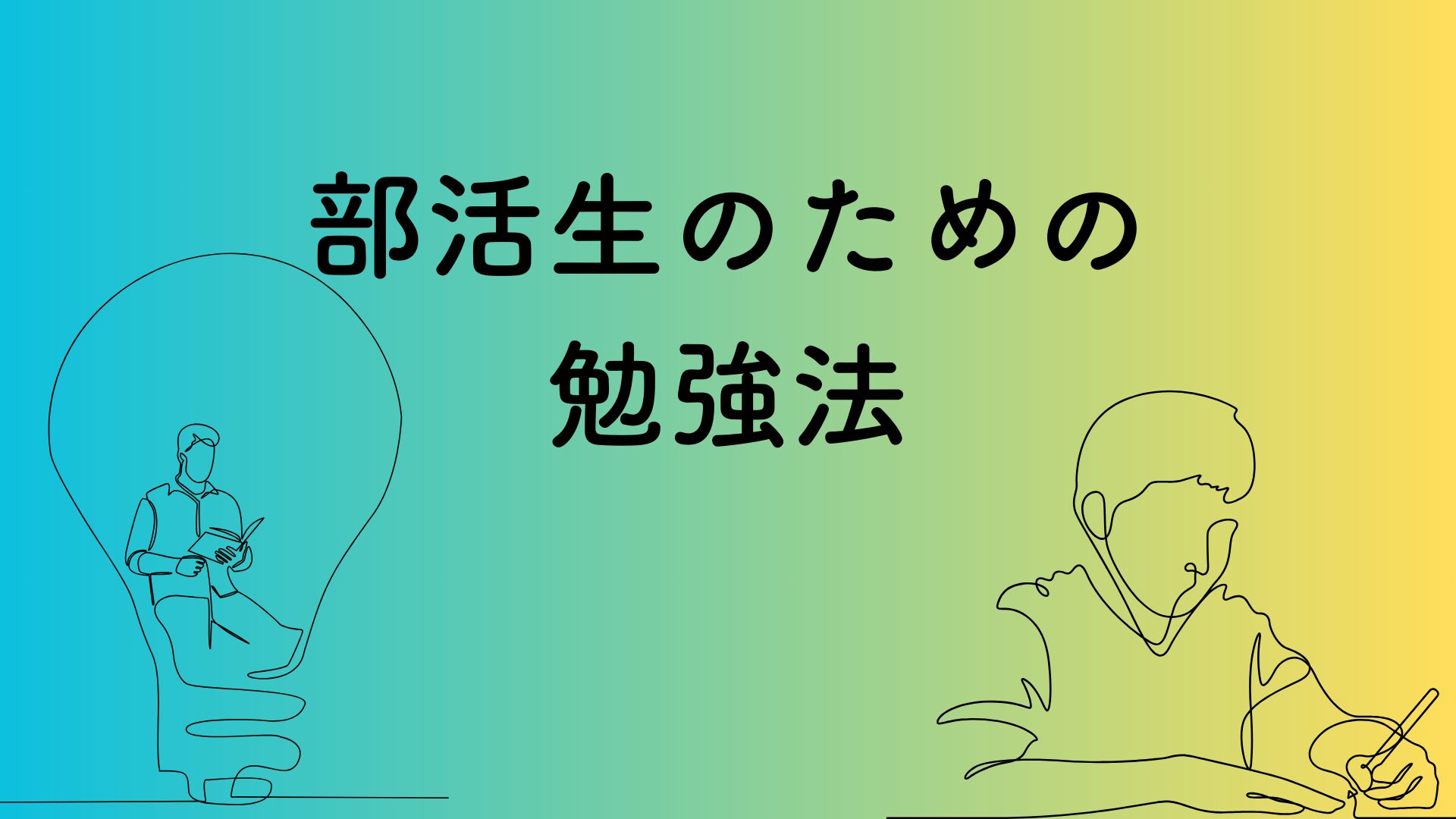【第1学年】定期テスト結果から見えた課題と今後の対策|親のリアルな振り返り
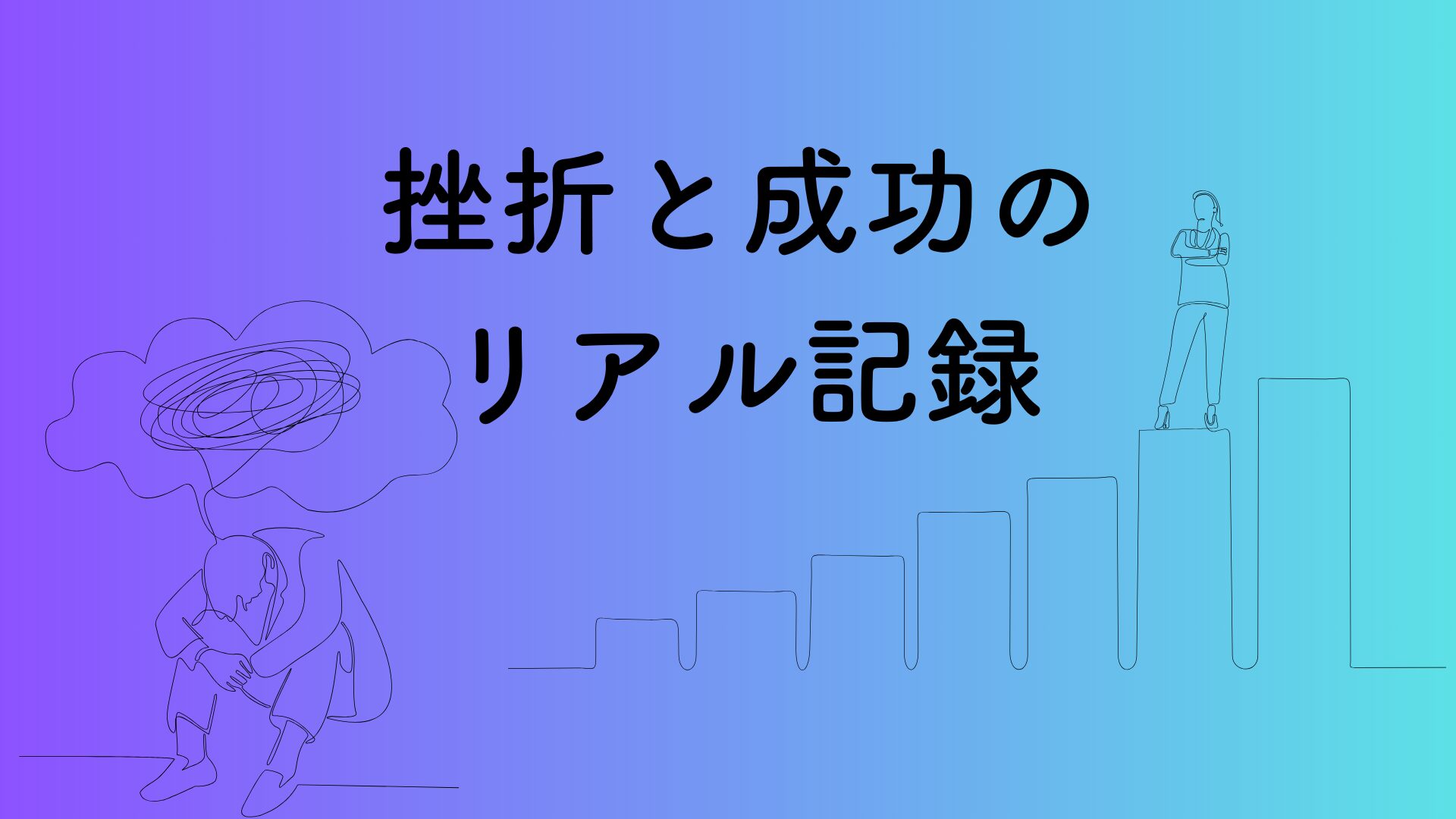
高校1年の定期テストを終えて思うこと
高校1年生の息子の定期テストがすべて終了しました。率直に言えば、この1年間の成績は期待したほど伸びませんでした。特に1学期の最初のテストでつまずき、その出遅れを1年間取り戻せなかった印象です。
本人は部活と勉強の両立に努力していましたが、中学時代からの成績の壁を越えることはできませんでした。親としては、日々机に向かう姿を見るたび「頑張っているのになぜ結果に結びつかないんだろう」ともどかしく感じることが多かったです。
この1年間の結果を踏まえて、息子の学習状況や成績推移を客観的に整理し、来年度への課題を見つけていきたいと思います。
中学と高校の「定期テストの違い」
この1年を振り返って最も痛感したのは、「中学と高校では勉強のやり方が全く違う」ということです。
中学の定期テストは授業内容をワークで復習し、テスト前1〜2週間ほど集中して勉強すれば、ある程度の点数は取れました。しかし、高校のテストは勉強量や質が格段に高く、授業で習った内容を一度や二度復習した程度では結果に結びつきません。
また、部活動や公式戦がテスト期間と重なることも多く、直前に集中して取り組むスタイルは高校では通用しないことがわかりました。親として、もっと早くその違いに気づき、早期に対応すべきだったと反省しています。
勉強習慣はあるのに、成果が出ない理由
息子の成績が伸びなかった原因の一つに、「勉強法が十分定着していなかったのではないか」と感じています。
この1年間を振り返ると、勉強する習慣自体はできつつありました。ただ、具体的に「何を」「どれくらい」「どのように」学習すれば定着するのか、その方法がまだ本人の中で明確ではないように見えました。
実際、定期テスト前にワークや教材を一通りやってはいましたが、それが十分な回数だったか、知識の定着に至っていたかというと、少し疑問が残ります。「一度解いた問題を繰り返して復習した方がよい」とアドバイスはしてきましたが、本人がその意図を理解し、実行できる環境を作る工夫が足りなかったのかもしれません。
こうした勉強方法については、もう少し親として具体的にフォローできればよかったと感じています。
親のサポートの限界と、第三者の必要性
1年間の息子の学習を見守る中で、親としてのサポートにも限界や迷いを感じる場面がありました。
個別の科目や問題に関しては、質問を受ければ答えることはできます。しかし、成績そのものを向上させるための具体的な勉強方法を伝えるのは、思った以上に難しいと感じました。また、本人の気持ちに踏み込むことが難しく、「このままではまずい」という本人の危機感や本気度がどの程度なのか、正確にはわからないことも悩みの一つです。
息子自身が「高校のテストでも点は取れない」と諦めているように見える時もありました。そうした気持ちに対して、親だけで支えることには限界を感じており、もしかすると第三者、例えば塾や専門のアドバイザーの力を借りた方がよいのかもしれない、と最近では考えることもあります。
来年度に向けた課題と、親としての葛藤
この1年を振り返り、課題や反省点がいくつも見えてきました。来年度に向けて改善するためには、いくつかのポイントがあると感じています。
まず、「勉強方法」の面では、一度やった問題を確実に定着させるための反復学習の仕組みを、本人が無理なく取り入れられるよう工夫したいと考えています。
また、本人がどこかで「自分は定期テストで点が取れない」と思ってしまっているようにも見える場面があり、そのままにしておくのは少し怖さを感じます。本人の“気づき”や“覚悟”を待っているうちに、あっという間に受験期に入ってしまい、結局あとから親も本人も苦労する、という展開は避けたいという気持ちもあります。
正直なところ、経済的に余裕があれば「任せてしまって、浪人するならそれも経験だ」と思えたかもしれません。でも、現実にはそうもいかず、そういった意味でも「いま関与するかどうか」が悩ましいところです。
私自身、2浪して大学に入りました。親からはある程度任されていたこともあり、高校時代は部活をイヤイヤながら続け、しかも、勉強は全くしておらず、結果として勉強の方法もわからないまま、何も積み上がらない3年間を過ごしました。そして浪人しても、「どう勉強すればいいのか」がわからないまま時間が過ぎ、ようやく大学にたどり着きました。
だからこそ、息子には「絶対に現役で受かれ」と思っているわけではありません。でも、現役合格を本気で目指すからこそ、学びの質や意識が変わってくるのではないか、そう思っています。
次の1年では、「学習法の定着」「本人の意識改善」「親以外の支援」の3つを軸に、親子で模索を続けながら、現役合格を“ひとつの目標”として意識していこうと考えています。
おわりに|うまくいかなくても、記録し続ける意味
高校1年生の1年間を振り返ってみて、親として多くの課題と学びがありました。定期テストの結果がなかなか振るわなかったのは事実ですが、それ以上に大切なのは、「どうすれば伸びるのか」を親子で模索し続けたこの過程だったようにも感じています。
中学と高校では、学習内容も試験の難易度もまるで違います。その違いに早く気づき、早く対応することができていれば――そう思うこともありますが、振り返ってみて初めて見えることもあるのだと、今は思えるようになりました。
学習習慣は少しずつ身につきつつある一方で、成績に結びつく「勉強のやり方」が定着しないもどかしさ。本人の中にあるかもしれない「諦め」の気配と、そこにどう関わればいいのか悩む親の迷い。そして、私自身が過ごしてきた浪人生活の記憶と重なり合いながら、「現役合格を目指す意味」についても、改めて考えさせられました。
このブログは、「家庭学習で逆転を目指す」という思いから始めました。でも現実は、そう簡単ではありません。それでも、**だからこそ書く価値がある。記録する意味がある。**そう思っています。
次の1年も、うまくいかないことの方が多いかもしれません。それでも一歩ずつ、試行錯誤しながら前に進んでいく――そんな日々の記録を、これからも綴っていきたいと思います。